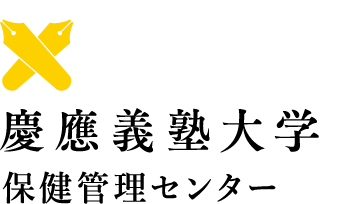大学講義
(1)学部(保健管理センター設置講座 講義場所:三田キャンパス)
ア 現代社会と医学Ⅰ「健康と安全の医学」春学期・秋学期(三田) 月曜 4 時限
コーディネーター 保健管理センター教授 森 正明
広瀬 寛、井ノ口美香子、佐渡充洋、牧野伸司、西村知泰、中村真理、康井洋介、葭葉茂樹、西村由貴(春学期)、後藤伸子、片山奈理子、三戸麻子
森 正明
・呼吸器感染症
・食中毒
広瀬 寛
・糖尿病について
井ノ口美香子
・がんに関する基礎知識
佐渡充洋
・マインドフルネス
・産業精神保健(秋学期のみ)
牧野伸司
・心臓突然死を防ぐAED
西村知泰
・喫煙と健康問題,肺がん
中村真理
・検尿・血圧について
康井洋介
・ワクチンで予防できる病気について
葭葉茂樹
・先天性の病気と現代社会
西村由貴
・現代社会と精神医学(春学期のみ)
後藤伸子
・アルコールのリスクを考える
片山奈理子
・うつ病について
三戸麻子
・プレコンセプションヘルスケア
イ 現代社会と医学Ⅱ「医学分野での現代のトピックス」
春学期・秋学期(三田) 火曜 4 時限
2024年度は休講
(2)学部(体育研究所設置講座 講義場所:日吉キャンパス)
体育学講義Ⅱ「健康とスポーツの科学」秋学期(日吉) 木曜4限
コーディネーター 体育研究所教授 山内 賢,保健管理センター教授 井ノ口美香子
横山裕一、武田彩乃
山内 賢
・健康について考える
・運動実施の効果、健康関連体力向上の方法と評価
・健康関連体力に繋がる歩行能力のはなし
・トレーニングを科学する
・スポーツ・運動実施上の安全管理の講話とBLS実習
・健康に関するSDGsを議論する
横山裕一
・飲酒の害
・依存症(薬物・スマホ)
井ノ口美香子
・内分泌代謝疾患
・小児の肥満、生活習慣病
・発達障害
武田彩乃
・高血圧
・脳血管疾患、てんかん
・性感染症、妊娠の知識
(3)学部(文学部・経済学部・商学部・薬学部講座 講義場所:日吉キャンパス)
「生命の科学」春学期 金曜1時限
コーディネーター 医学部公衆衛生学教室教授 岡村智教
佐渡充洋
・マインドフルネス
他
(4) 学部(文学部講座 講義場所:三田キャンパス)
「精神医学」秋学期 月曜4時限
コーディネーター 医学部准教授 藤澤大介
佐渡充洋
・第9回 マインドフルネス認知療法
・第10回 認知症の進展予防
・第11回 産業精神保健
他
(5) 学部(医学部講座 講義場所:信濃町キャンパス)
「感染症学」秋学期 月曜3時限他
長谷川直樹、新庄正宜、西村知泰、上蓑義典、南宮 湖、吉藤 歩、宇野俊介
西村知泰
・抗酸菌感染症(結核菌および非結核性抗酸菌)
・感染症法と現代の感染症、新興・再興感染症、職業感染対策と保健管理センターの役割
他
(6) 学部(医学部講座 講義場所:信濃町キャンパス)
「小児科学」春学期(信濃町)
鳴海覚志、高橋孝雄、新庄正宜、明石真幸、長谷川奉延、山岸敬幸、小崎健次郎、嶋田博之、肥沼悟郎、武内俊樹、幡谷浩史、石井智弘、飛彈麻里子、福島裕之、井ノ口美香子、古道一樹、有光威志、冨田健太朗、三橋隆行、小柳喬幸、住友直文、山﨑文登、中村俊一郎、古市宗弘、井口智洋
井ノ口美香子
・小児保健、学校保健
他
(7) 学部(医学部講座 講義場所:信濃町キャンパス)
「精神医学講義」春学期 特定期間集中
コーディネーター 医学部精神神経科学教室准教授 村松太郎
佐渡充洋
・第18回 産業精神医学
他
(8) 学部(看護医療学部講座 講義場所:信濃町キャンパス)
「慢性期病態学 呼吸器疾患」春学期(信濃町) 水曜2時限他
森 正明、西尾和三、中村守男
森 正明
・呼吸器の解剖と生理
・呼吸器疾患の検査と診断
他
(9) 学部(学生総合センター設置科目 講義場所:全キャンパス,e-learning)
「大学生活における責任と危機管理」春学期前期・春学期後期・秋学期前期・秋学期後期
横山裕一、西村由貴、西田公昭、濱田庸子、根本 彰、神田武志、矢田部菜穂子、堀 成美
横山裕一
・飲酒事故予防のために
西村由貴
・薬物乱用と問題使用
(10)大学院(健康マネジメント研究科 講義場所:信濃町キャンパス)
「精神保健」春学期前半 木曜日5,6時限
コーディネーター 保健管理センター教授 佐渡充洋、総合政策学部教授 島津明人
佐渡充洋
・第1回 精神保健概論(1)
・第2回 精神保健概論(2)
・第5回 職場の復帰支援(1)
・第7回 認知症
・第9回 マインドフルネス概論
・第10回 マインドフルネス実践
他
(11) 大学院(健康マネジメント研究科 講義場所:信濃町キャンパス)
「医薬経済学」春学期 木曜日 6,7 時限
コーディネーター 健康マネジメント研究科特任教授 稲垣中
佐渡充洋
・第7回 日本における認知症の社会的コスト
他
(12) 大学院(健康マネジメント研究科 講義場所:信濃町キャンパス)
「ヘルスアウトカム評価論」秋学期 土曜日5,6時限
コーディネーター 看護医療学部教授 山内慶太
佐渡充洋
・第7回 インフォーマルケアのコスト(認知症を例として)
・第8回 生産性損失の費用(うつ病を例として
他
(13) 通信教育課程(夏期スクーリング 講義場所:日吉キャンパス)
「麻疹・風疹」 井ノ口美香子【目的】以前は主に小児の感染症であった麻疹、風疹は、近年では感染者の大部分が成人に変化している。最新の流行状況、様々な合併症、予防について学ぶ。
「地球史、人類史から考える現代の疾病」 横山裕一【目的】ホモ・サピエンスは20 ~ 40 万年前に地球に誕生したが、現代においても、基本的に当時の生活スタイルに適合した生物のままであることを理解し、当時のスタイルが失われた現代社会での生活が種々の生活習慣病の原因になっていることを学ぶ。
「虚血性心疾患」 牧野伸司【目的】虚血性心疾患は生活習慣病の最終的直接死因のひとつであり,突然死の原因としても重要である。その病態,予防,緊急時の処置について学ぶ。
「生活習慣病」 広瀬 寛【目的】最近のライフスタイルの変化が糖尿病や高血圧を増加させている。これら生活習慣病の正しい理解とその予防・治療について学ぶ。
「感染症」 森 正明【目的】インフルエンザ,結核,食中毒など,日頃,健康な人でも注意が必要な感染症の予防や治療について学ぶ。
なお、講義のほかに通年レポート添削を、上記教員および西村知泰・武田彩乃・康井洋介・中村真理・葭葉茂樹・後藤伸子が行っている。