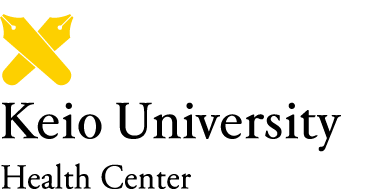春は送別会や歓迎会などでお酒を飲む機会がいつもより多くなる時期です。しかし、大変残念なことに、慶應義塾大学では2012年に続いて2013年にも大学生が飲酒の事故で亡くなるという痛ましい事故が発生しました。
●お酒が強い人、お酒が弱い人、お酒が飲めない人
同じお酒を飲んでもすぐに酔う人とあまり酔わない人がいます。飲酒で摂取したアルコール(エタノール)は、肝臓でアセトアルデヒドから酢酸に変化し、最終的に二酸化炭素と水に分解されます。エタノールがアセトアルデヒドから酢酸に変化する際には、体内のアルデヒド脱水素酵素の働きが必要ですが、人間にはこの酵素の「活性が強い人」、「活性が弱い人」、「活性が全くない人」の3種類が存在します。酵素の「活性が強い人」は「お酒が強い人」,「活性が弱い人」は「お酒が弱い人」,「活性がない人」は「お酒が全く飲めない人」にあたります。日本人の割合はそれぞれ56%、40%、4%と報告されており、日本人の約半数が「お酒が弱い人」または「お酒が全く飲めない人」にあたります。これらのタイプは遺伝で決まり,後天的に変化することはありません。「訓練をすれば飲めるようになる」というのは誤りです。「お酒を飲むと顔が赤くなる」,「胸がドキドキする」,「眠くなる」などの症状がある人は、自分の体質を理解し,また周囲の人にも理解してもらい,体質に応じた飲み方をすることが大切です。
一方,「お酒が強い人」も,飲めるからといってたくさん飲むことが常習化するとアルコール依存症になる可能性があり,注意が必要です。また、その日の体調なども影響し,いつもと同じ量が飲めないこともありますので,決して無理はしないことが大切です。
●急性アルコール中毒
平成24年に東京消防庁管内において急性アルコール中毒で救急搬送された人は約12,000人で,そのうちの約半数が20歳代です。その理由として,グループで飲む機会が多いこと,また自分の適量が分からず無謀な飲酒をしてしまうことがあげられます。無謀な飲酒から急性アルコール中毒になり,死亡することもあります。急性アルコール中毒にならないために正しい知識を持ち,万一なってしまった際の応急処置を知っておく必要があります。
- 1.「一気飲み」や「コール」など短時間に大量の飲酒をしない
- 若年者はエタノールの分解能力が低く,血液中のエタノール濃度が一気に上がり危険です。
- 2.酔った人がいた時には、目を覚ますまで周囲の人が付き添い,決して一人にしない
- 吐物で窒息しないように、横向きに寝かせ、「呼びかけても反応しない」、「つねったりしても痛み刺激に反応しない」、「からだが冷たい」などの症状を認めた場合にはすぐに救急車を要請してください。
●アルコールハラスメント
アルコール薬物問題全国市民協会では、「飲酒の強要」、「一気飲みの強要」、「意図的な酔いつぶし」、「飲めない人への配慮を欠くこと」、「酔った上での迷惑行為」の5つをアルコールハラスメント(以下アルハラ)と呼んでいます。この協会が2013年に実施したアンケート調査では,一年以内に自分がこれらの行為に関わったことがある、あるいは実際に飲まされた経験のある人は55.1%、周囲でこれらを見たことがある人は69.0%で、かなり高い割合でアルハラが行われています。一方、「アルハラを断ることができるか」の質問には、33.9%が「断れない」、26.7%が「わからない」と回答し、「自分だけが断って空気を読めないと思われたくない」、「周りのみんなも飲むので自分だけは断れない」を主な理由としてあげています。
無謀な飲酒は、自分たちが飲酒による事故を起こしそうな状況にあることの判断をむずかしくし、結果的に不幸な事故を引き起こすことにつながります。
もう一度自分たちの飲酒行動を見直してください。