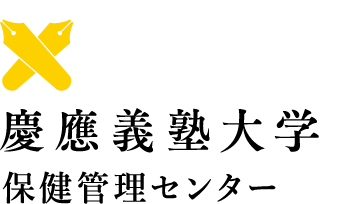"生活習慣"病とは
生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因となりうる疾患の総称です。日本人の死因の上位を占める、がんや心疾患(心筋梗塞や狭心症)、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血、くも膜下出血)が、生活習慣病に含まれます。これらの疾患には体質などの遺伝的背景も関与しますが、研究の結果、いわゆる「健康的」と言われてきた生活が、生活習慣病の予防および病態改善に有効であることがわかってきました。忙しい毎日をお過ごしかと思いますが、可能な範囲で調整しましょう。また時には、これまでの優先順位を見直し、がらりと生活を変える勇気も必要かもしれません。ご自身の将来のために健康的な生活を心がけましょう。
「健康的」な生活習慣とは
- その1 禁煙
- 喫煙は健康にさまざまな悪影響をもたらします。また喫煙の害は喫煙者のみならず、周囲にいる人にも及びます。
- その2 食事
- 食事は毎日の健康の要です。できるだけ規則正しくとりましょう。塩分を控えめに、脂っぽい食事は避けましょう。調味料の使用を控えたり、下茹でや湯通しする、蒸して食べるなど、調理方法を工夫したりするのもおすすめです。主菜は肉より魚を心がけましょう。野菜を多くとりましょう。大豆製品や発酵食品の摂取もおすすめです。痩せすぎも様々な病気を引き起こします。適切な栄養素とエネルギー量を確保しましょう。
- その3 適度な運動を毎日続けましょう
- まずは今より少しでも多くからだを動かすことから始めましょう。座りっぱなしは避け、1時間に1回は席をたったり、軽い体操をしたりしましょう。家事も大切な運動です。無理しない程度に、毎日続けましょう。
- その4 睡眠(休養)
- 睡眠には、疲れた身体をリラックスさせ、疲労を回復させる効果があります。夜ふかしを控え、規則正しい睡眠をとりましょう。疲れを感じるなら、睡眠時間を1時間増やすのを、2週間ほど続けてみましょう。眠れない、途中で何度も起きてしまう、息が止まっている、いびきがひどい、などあれば医療機関で相談しましょう。
- その5 減酒
- お酒は中性脂肪を増やしたり、血糖を上昇させやすくしたりするなどの作用があります。また、睡眠の質をさげてしまいます。年齢とともに、できるだけお酒の量は控えましょう。
- その6 ストレス対処
- 過度なストレスが続くと、健康のバランスを崩す原因にもなります。仕事も学業も、身体を壊しては何もなりません。現在の負荷が適切かどうかの見直しと整理を行いながら、自分に合ったリラックス方法を見つけて、早めに対処しましょう。
- その7 歯の健康
- 毎食後、歯を磨きましょう。むし歯や歯周病は自覚症状がないまま進行します。予防には、毎食後のていねいなブラッシングと定期的な歯科受診が効果的です。
どんなことに気を付けたらよいでしょうか
最近、疲れやすい、体力が落ちた、疲れがとれないなどを感じることはありませんか。まずは、学校や職場の健康診断を受けましょう。気になることがあれば保健室や保健管理センターでご相談ください。日頃から、鏡を見たり、体重計に乗ったり、血圧を測ったり、とモニタリングと記録を行いながら自分の体調変化や異常に気づくようにしましょう。
参考資料
1)e-ヘルスネット 生活習慣病とは?
2)全国健康保険協会:生活習慣改善10か条
3)慶應義塾大学保健管理センター:健康情報シリーズ「在宅勤務における健康管理」
http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/health/2020/05/health-management-when-working-from-home.html
4)慶應義塾大学保健管理センター:健康情報シリーズ「バランスの良い食事とは?」
http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/health/2020/05/what-is-a-well-balanced-meal.html